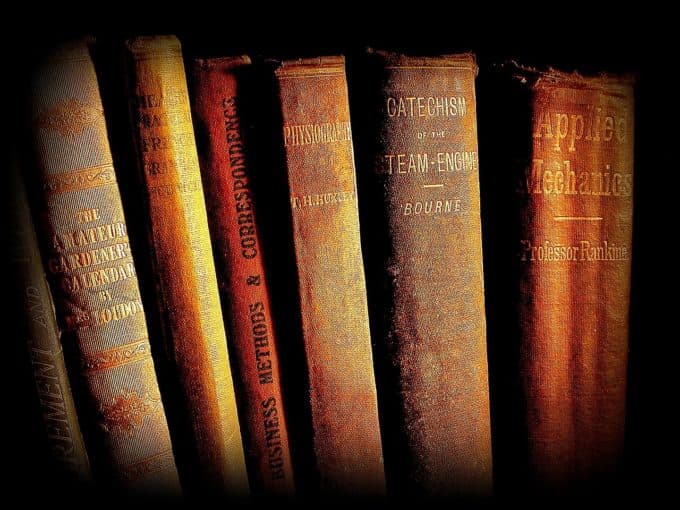
サイコキラー・サディズムプレイ
2018年6月13日
思いがけない収穫……いや、新たな性癖の開拓……いやいや、開発か。
うまいこと言ったもんだ。俺はニヤニヤと笑いながら、親指でこするように、唾液でぬめった唇をぬぐった。まるで野良犬の交尾を偶然、目撃したように、奇妙な高揚感と不思議な歓びがあった。
なんのことはない。休日、俺は一人で、レンタルビデオ店で借りてきたホラー映画を観たのだ。
正直、暇つぶし意外の何者でもなかった。非正規の週六肉体労働。せっかくの週に一度の休みの日だというのに、家で過ごすしかないというのがしけていた。
給料日当日にパチンコにも負け、風俗に行く金もない。ドライブに出かけるガソリン代すら惜しい。さりとて家にこもっているのが大嫌いな俺は、徒歩数分の場所にあるビデオ屋に足を向けたのだった。
しかし、地元のビデオ屋にあるAVは、ほとんど借り尽していた。色んなジャンルを毎日観ているが、さすがの俺でも飽きる。
そこで奇をてらって選んだのが、ホラー映画だった。
ホラーとエロは表裏一体だという。
なるほど、その理由はわかる。B級ホラー映画なんかは、エロイねーちゃんが殺されるというのが定番だ。それは殺伐とした映画のオアシスのようなもので、サービスシーンだ。
むろん、AVに比べてズリネタにはなりはしないだろうけど、今日は暇つぶしだ。それでいい。
俺はB級ホラー映画を借り、昼間からビール片手に鑑賞会としたのだが……。
いや、油断していた。
俺を待っていたのは、金髪オネーチャンの裸ではなかった。
むしろ、サービスシーンは全くなかったといっていい。ただ死んだはずのサイコキラーが、子供たちを延々と殺戮していく、という内容だった。
特に盛り上がりもなければ、意外な展開もない。俺が拍子抜けしながらビールの缶を潰した頃。
とあるシーンが、俺を釘づけにした。
それは、くだんのサイコキラーが、元薬物ジャンキーのネエちゃんを殺す、というシーンだった。
抵抗するオネーチャンを易々と縛り、サイコキラーが指の間に注射器を構える。ジャンキーだった過去を払拭しようとしているオネーチャンにとって、注射器は甘い誘惑と恐怖の象徴だ。
サイコキラーが構える注射器、その数、六本。注射器には致死の猛毒でも入っていたのだろうか、サイコキラーが六本全てを縛り上げたままのオネーチャンに刺しいれる。サイコキラーの恍惚とした顔。オネーチャンはジタバタと抵抗しながら死に至る……。
そんなシーンを観た俺は、股間を押さえながら慌ててトイレに駆け込んだ。
トイレにかけこみ、即座にイッてしまう。ほとんどしごく必要もなかった。
めちゃくちゃ興奮した。
ホラー映画に詳しくないとしても、視ていた人間はあのシーンが射精の暗喩ということに気づいただろう。
例えるなら、ジャンキーのネエちゃんは、性に奔放な元ヤリマン。サイコキラーは死んだはずの連続強姦魔としよう。
連続強姦魔に襲われ、禁欲中の元ヤリマンがプレイのなかで歓びを覚え、よがり声も堂に入ってくる。
久しぶりの女を味わった強姦魔はぞんぶんに射精しながら、「なんだ、まだ好きなんじゃないか」と嬉しそうにつぶやく。
そんなエンディングにでも置き換えられるだろうか。
素晴らしい。
俺はAV監督になれるんじゃないか。
そして、監督になるよりも前に、当然の欲求が頭をよぎった。
俺も、あんなプレイがしてみたい。
指に注射器を持って、ドロッドロの精液を女の膣内に入れたい。
心を決めた俺の行動は速かった。
早速、その日の晩にソープへ出向く。受付で嬢を指名するよりも前、開口一番に俺は言った。
「あ、あのですね、ちゅ、注射器をね、刺したいんですよ、嬢に。六本。そんな、プレイをしたくてね、」
プレイどころか俺が警察に連れていかれそうになった。
良くよく考えれば、そりゃそうだ。「精液のたっぷり詰まった注射器を嬢の身体に刺させてくれ」なんて、金をもらっても絶対にやりたくない。
スタコラ逃げた俺は、家で、作戦会議をすることにした。
まず、注射器を揃えようと思う。それも六本だ。多すぎるようだが、そこだけは譲れない。
俺は次の日の朝、百円均一へ行って、おもちゃの注射器を六本、買った。袋から出したばかりのそれを、指の間に挟めてみる。
「フフフ」
怪しげな笑みを浮かべてみると、口の端が釣り上がった、いかにも殺人鬼らしい笑い方になった。演技は完璧。
しかし、本当の苦難はこれからだった。
俺は笑みをひっこめ、袋から出したプラスチックの図太い注射器をことりと置いた。
その、何も入っていない空洞の中身をじっと眺め、俺は内臓を唸らせた。
……無理だ。
注射器六本分、六本分の精液か。
これはなかなか手ごわい。全盛期の中学生の俺でも、六本はきつい。一日一本として、まさかザーメンを冷凍保存しておくわけにはいかないだろう。汚いし、嫌だし、そんなものを保管していた冷蔵庫なんて金輪際使いたくない。よく誤解されるが、俺は清潔なのだ。
「くっっっそぉおおおお」
俺は頭をかきむしった。
なんてコストがかかるんだ、サディズムプレイ。冗談じゃない。来月だって支払いがあるっていうのに。これ以上金はかけられない。
俺は一人、部屋に篭って、ない頭を必死に動かしまくった。会社を休んで、もう来なくていいと怒鳴られた。構って居られない。俺はこのプレイに、人生の、情熱の、全てをかけているんだ。
そして、七日が経った。
「こんにちはぁ」
七日目の夜、ついに俺はデリヘル嬢をアパートに招いた。エラが張った女だが、胸が大きい。決して美人ではないが、全体的にスタイルが良くて、腰が細いのがなにより気にいった。
シャワーを借りようとする嬢を俺は後ろから捕まえて、無理やりベッドに押し倒した。
当然ながら、まだ濡れていない。が、俺はパンツをはぎ取って、ブツをあてがう。
痛い、と不機嫌そうに顔をしかめた嬢だったが、俺の手にしたモノを見て目を丸めた。
「なぁにぃ、それ」
「ヒヒヒ」
俺は答えず、注射器を押した。先端から白濁した液体が押しだされて漏れた。
その様子を見ていた嬢は、楽しそうでありひきつっているような、奇妙な顔になった。そう、まるで犬の交尾を見たときのような。
いけるクチだな、と俺は笑った。そして嬢のパンツをはぎ取った。
さっきまで乾いていたはずの入り口は、しっかりと濡れていた。俺はガチガチに硬くなっていたブツをバックから乱暴に挿入する。
お互いに、奇妙な高揚があった。
俺も、嬢も、激しく腰を振り合い、求めあった。多くの時間をかけないうちに、すぐ限界を迎えようとしていた。
「刺すぞ、刺すぞぉ」
俺は達する寸前で、注射器を何度も取り落としそうになりながら、女の身体に突きたてた。
あああ、これだ、この瞬間だ!
むろん、おもちゃの注射器で中の白濁が流し込まれる訳もないが、女は快感に身を震わせ、腰を浮かせた。
「ああッ……」
弛緩した裸体に、俺は力の限り、注射器を押し出した。同時に、ゴムのなかに思いっきり精液を吐き出す。
最高の幕引きだった。
びくびくと震える嬢の身体に、注射器から出された白い液体がべっとりと付着している。
俺は賢者タイムに浸る前に、すぐさま、ウェットティッシュで女の身体を拭いてやる。
力をなくした女が嬉しそうに笑った。
「ふふ、……可愛い、おもちゃ」
妖艶に笑いながら、嬢は注射器の先端をしゃぶった。やめてくれ、と心の中で哀願する。そんなことを、そんなことをされたら、またハマっちまうじゃないか。
注射器を口内から名残惜しそうに解放した嬢が、ふと冷静になって言う。
「ねぇ、これ、六本あるでしょ? すごいよね」
「すごいって?」
俺はベッドの上に座りながら、横たわる嬢を見下ろした。嬢はいくぶん、尊敬のようなものを滲ませて俺を見上げて言う。
「六本分出すのが、さ。だいぶ溜めてからシてるの? 一日に何度も?」
俺は曖昧に笑う。
世の中、知らないことがいいこともある。
俺達の座るベッドの下、小さなボトルがある。
“洗濯のり”と書かれたそのボトルに感謝しながら、俺は満足気に息を吐いた。
完
